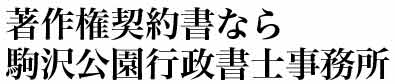棋譜の著作権
碁や将棋の対局の記録である棋譜。
日本将棋連盟のサイトをみると、「棋譜の表記方法」として表記方法にルールがあることが分かります。
日本将棋連盟TOP>よくある質問>棋譜の表記方法
https://www.shogi.or.jp/faq/kihuhyouki.html
チェス、囲碁、将棋などのボードゲームの棋譜の著作権を考える場合、アイデア自体なのか、表記自体なのか、表記に基づいたコンテンツのことなのかは分けて考える必要があります。
2020年4月17日、日本将棋連盟は、会長名で質問に対する回答を公開しています。
「棋譜利用に関する公開質問状への回答」
https://www.shogi.or.jp/news/2020/04/post_1908.html
「【回答】
棋譜の著作権の有無に関しまして、様々な議論があることは承知しておりますが、日本将棋連盟と各棋戦共催社及び主催社(以下「主催社」)間では棋戦運営するにあたり、主に棋譜の優先掲載に関する契約を結んでおります。
弊社団は日本の文化たる将棋の発展を目的としている団体であり、棋戦運営は事業の根幹を成すものです。棋戦を運営する前提として、弊社団及び主催社等には、棋譜の利用も含む営業上の利益を有しており、これは法的に保護される利益であると認識しております。」
こちらにありますように、棋譜の著作権について、確定的な裁判例はありませんで、一般論からすれば、棋譜自体は戦術の類いはアイデアとして、また、アイデアを一定のルールで表現した記録についてもありふれたものとして著作権では保護されないものといえます。
もし、仮にこれを著作権として保護しますと、その手を思いついた人がその手の利用を独占することになって、第三者は同じ手を指すのに創作者から許諾を得なければならなくなり、それはいかにも不合理であることからも分かります。
もっとも、著作権で保護されないものも、不正競争防止法や民法の一般不法行為論(709条)などで保護される場合があります。裁判例でも「法的保護に値する利益」というフレーズで、著作権で保護されない場面でも民法の不法行為論のなかで保護する余地を認めています。
1例として、ヨミウリオンライン事件(知財高裁平成17年10月6日判決平成17(ネ)10049著作権侵害差止等請求控訴事件)があります。
「不法行為(民法709条)が成立するためには,必ずしも著作権など法律に定められた厳密な意味での権利が侵害された場合に限らず,法的保護に値する利益が違法に侵害がされた場合であれば不法行為が成立するものと解すべきである。」
最高裁判所サイト https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/009350_hanrei.pdf
日本将棋連盟の回答もこの点を踏まえており、従前の契約関係などから営業上の利益がある場合、「法的に保護される利益」として保護されると示しているわけです。
なお、棋譜を利用して解説文を作成したり、動画を制作すれば、それらに別途著作権が発生して作成者が著作権者となることは充分考えられますが、それはまた別の場面の話しとなります。
■参考判例
将棋動画虚偽事実告知事件(個人対株式会社囲碁将棋チャンネル)
大阪地裁令和6.1.16令和4(ワ)11394不正競争行為差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/092676_hanrei.pdf
「本件は、原告が、ユーチューブ等に投稿した別紙「原告動画目録」記載の動画(以下、順に「本件動画1」などといい、これらを「本件動画」と総称する。)について、被告がグーグル等に対して本件動画が被告の著作権を侵害する旨の申告をした行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の不正競争に当たると主張して、被告に対し、不競法3条1項に基づき、原告が配信する動画が被告の著作権を侵害する旨を第三者に告げることの差止め(前記第1の1)、同法14条に基づき、グーグル等の動画配信プラットフォーム事業者(以下「プラットフォーマー」という。)に対して本件動画が被告の著作権を侵害しないこと等を通知すること(前記第1の2及び3)を求めるとともに、民法709条に基づき、損害賠償金338万8360円及びうち312万4510円に対する令和4年1月10日(本件動画1ないし9に係る最終の不法行為の日)から、うち26万2350円に対する令和5年1月8日(本件動画10に係る不法行為の日)から各支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払(前記第1の4)を求める事案である。」
*当事者が棋譜の著作物性を争点としていないため、不正競争防止法からの判断の事例となります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 著作権2020年4月27日遠隔授業と著作権
著作権2020年4月27日遠隔授業と著作権 著作権2020年4月20日絵本の読み聞かせと著作権
著作権2020年4月20日絵本の読み聞かせと著作権 著作権2020年4月18日棋譜の著作権
著作権2020年4月18日棋譜の著作権 知的資産経営2019年9月1日お酒が呑めたらなあ・・・
知的資産経営2019年9月1日お酒が呑めたらなあ・・・

駒沢公園行政書士事務所
〒145-0064 東京都大田区上池台1-34-2
TEL:03-6425-7148
FAX:03-5760-6699
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
お電話受付時間:平日10時~18時(土日祝はお休み)